空襲で京都全市が火に包まれないか、明日こそ金閣が焼けるだろうと夢見るが、待てども待てども京都は空襲に見舞われない。
そのもどかしい想いを、三島はこう表している。
ともすると早春の空のただならぬ燦めきは、地上をおおうほどの巨木な斧の、すずしい刃の光のようにも思われた。私はただその落下を待った。考える暇も与えないほどすみやかな落下を。
そんな三島由紀夫の文章をノートに書き写している女子高生には、想像するだけでモノを実体化できる能力がある。


目には見えないけれど確かに存在するモノ。
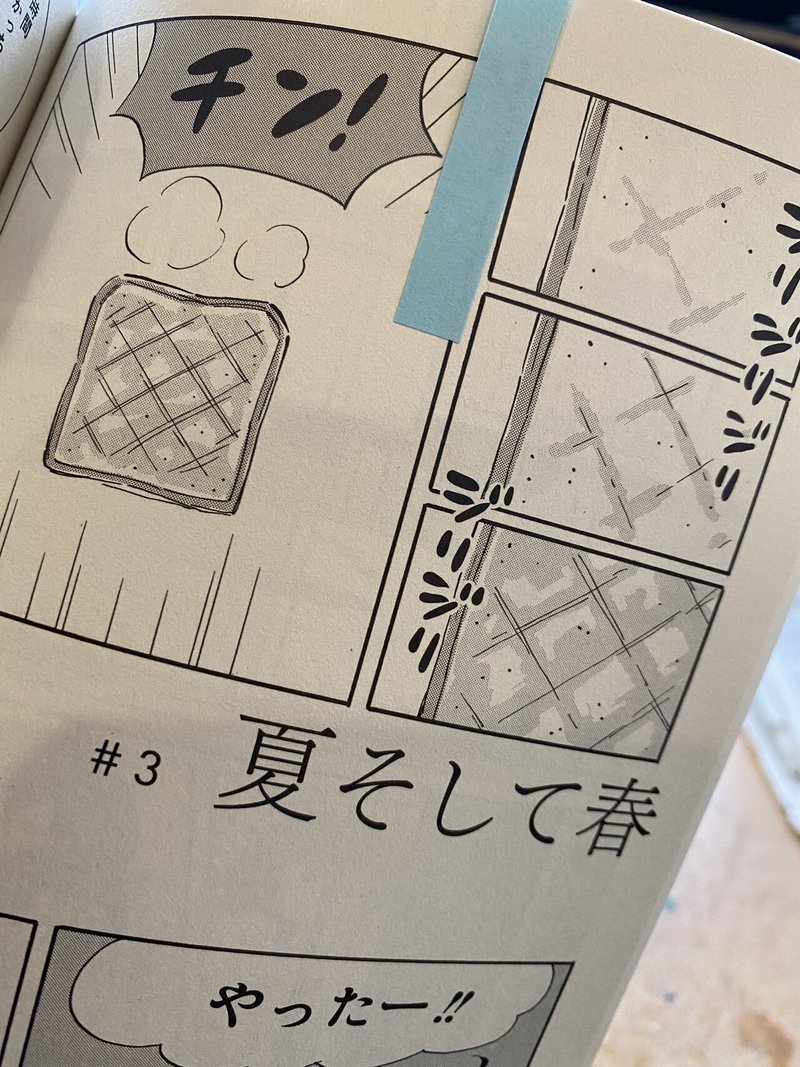

はじめはそんな能力をつかい、小さなはさみや傘、風船やトースターあたりを(見えないけれど)実体化していたけれど、徐々に危ない想像がはじまりかけてきた。
まだ第一巻。この物語はどこへ向かうんだろう。